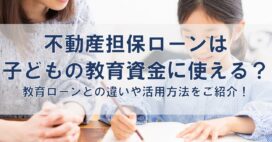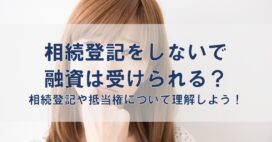離婚時に家をスムーズに財産分与する方法は?住宅ローンに関する注意点や手続きとは

夫婦間の婚姻関係が破綻に陥ってしまった場合、さまざまな法的手続きを踏まなければなりません。その中でも手続きに困難を強いられることが、不動産に関わる「財産分与」です。
「財産分与の対象範囲はどこまでを含めているのか」「分与の割合はどのように決定するのか」など、財産分与に関する疑問は離婚の局面に立ちはだかります。
そこで本記事では、財産分与の方法・住宅ローンが残っている場合の対処法・税金の種類について解説します。
目次
家を財産分与する方法
家・マンション・土地などの財産分与に当たり、最初に確認すべき点は「婚姻関係にある期間に所有したもの」であることと、「夫婦共同で購入した」という2点です。親からの相続や、独身時代に所有したものについては財産分与の対象から除外されます。
離婚時の財産分与対象については折半が原則です。しかし、財産分与の割合は話し合いで変更も可能であり、家庭ごとの事情によって割合に変化が生じます。
売却
住んでいた家などを売却し、現金化し割合に応じて分配するパターンを多くの人が取り入れています。ただし、売却金額と貯金を合わせてもローン完済に至らない場合は、金融機関を通した任意売却を相談しなければなりません。また、任意売却は通常の不動産取引と同じ扱いになるため、裁判所を通した競売に比べ高値で売却できる可能性があります。
妻または夫どちらかが住み続ける
家を売却せずにそのまま住み続けるケースでは、住宅ローンが残っていることや、子どもの教育環境を変えたくないといった理由を多くの人が挙げています。住宅ローンが完済している場合は、住み続ける側の名義に変更しておきましょう。例えば、夫名義のまま妻が住み続ける場合、返済放棄や支払い不能などトラブルが起きることもあります。
こういったリスク回避のために、以下の方法を取るとよいでしょう。
- 妻名義で住宅ローンを借りたうえで、名義を妻側に変更する
- 夫と賃貸契約を結ぶことで、妻が残りのローンを家賃として払う
- ローン完済後に名義を夫から妻へ変更する契約書を交わしておく
住宅ローンが残っている場合の確認すべきポイント
| 確認すべきポイント | 確認方法 |
| 名義人 | 法務局で不動産の登記事項証明書を取得する
*抵当権の設定も確認しておく |
| ローンの名義人・残債・連帯保証人等 | 住宅ローン契約書類に記載されている
*書類がない場合は、借入先の金融機関で確認する |
| 不動産価格 | 数軒の不動産会社で査定依頼し、時価を把握する |
| 特有財産の有無 | 夫婦の共同財産とみなされない「特有財産」を把握する
*定義が難しい場合もあるため、弁護士に相談する |
| 財産分与の対象期間 | 婚姻届提出日から別居日までが一般的な期間 |
財産分与に伴う税金
離婚による財産分与に関しては「離婚により財産を分け合った」と定義づけされています。そのため、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。
参考:国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」
譲渡所得税
離婚の財産分与で注意しておきたいことは、不動産を取得した金額より売却した金額が上回った場合です。差額部分に譲渡所得税が発生します。譲渡所得税についての計算方法は、税理士へ相談しましょう。
贈与税
先述にもあるとおり、基本的には離婚時に不動産を譲り受けた際、贈与税はかかりません。ただし、以下の条件に当てはまる場合はそれぞれ税金が発生します。
- 財産分与の程度が夫婦の協力によって得たものやその他すべての事情を考慮しても多すぎると判断された場合。その際は、多すぎる額に贈与税がかかります。
- 贈与税や相続税の免除を受けるための偽装離婚だと判断された場合。その場合は、離婚による財産分与とはみなされず、譲り受けた財産すべてに贈与税がかかります。
参考:国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
登録免許税
例えば、不動産を「夫から妻への名義変更する」場合、変更時には発生します。不動産の所在地である登記官署などに納税義務があります。
参考:国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」
固定資産税
売却を行わず夫婦のどちらかが住み続けた場合には、毎年固定資産税が発生することも覚えておきましょう。
まとめ
離婚時の財産分与は揉めること多い傾向にあります。しかし、スムーズに財産分与を行わなければ精神的トラブルを招くだけではなく、財産分与の期限である「離婚後2年」の期限を過ぎてしまうことにもなります。離婚後のトラブルを回避するためにも、専門家である弁護士・税理士に早めに相談しましょう。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。