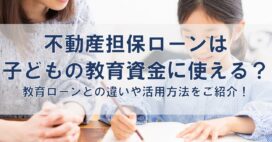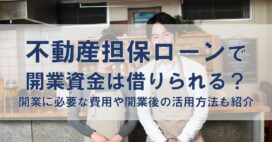不動産担保ローンの金利と抵当権とは?|ローンの基礎知識について解説
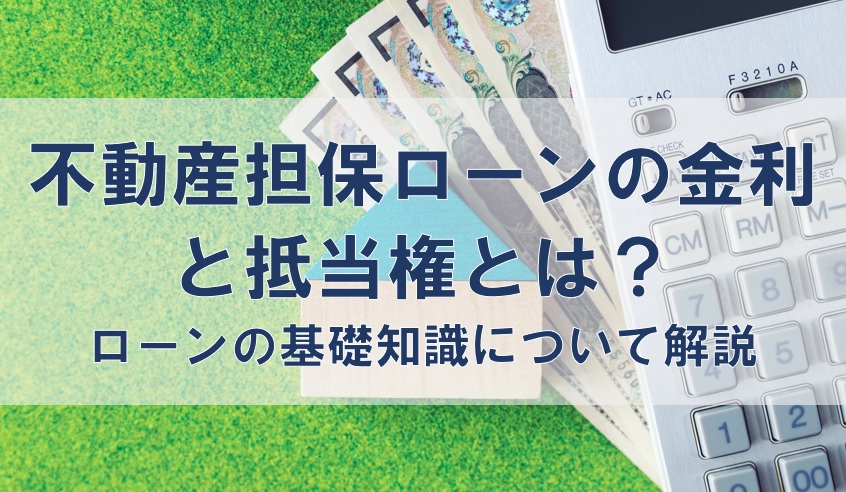
不動産担保ローンを利用する際、抵当権という言葉が出てきます。しかし、日常生活では馴染みのない言葉であることから、抵当権について知らないという方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産担保ローンの抵当権とは何かについて詳しくご紹介します。
目次
不動産担保ローンの「抵当権」とは
不動産担保ローンの抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に、購入する土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。抵当権を設定しておくことで、住宅ローンの返済が計画通りに行われなかった場合、債権者に損害が生じないように設定されます。
住宅ローンには必ずしも抵当権が設定されるという訳ではなく、中には抵当権を設定しない無担保ローンもあります。抵当権が設定される不動産ローンは「有担保ローン」、抵当権が設定されないローンは「無担保ローン」に分けられます。
抵当権を設定するタイミング
抵当権が設定されるタイミングは、住宅ローンで借入または借り換えをする際です。抵当権の登記手続きは司法書士に依頼するしか方法はなく、自分自身で行うことはできません。
基本的に金融機関や不動産会社が指定する司法書士で行われるため、借主に登記を依頼するケースはほとんどありません。なぜなら、登記手続きには専門的な知識が必要不可欠だからであり、万が一ミスがあった場合は無担保ローンになってしまうリスクがあるからです。
なお、登記手続きを司法書士に依頼すると、登記にかかる登記免許税に加えて司法書士に対する報酬も発生します。
抵当権付きの不動産は相続できる
抵当権が付いていても不動産を相続することは可能です。ただし、抵当権が付いたまま不動産を相続するということはローン残高があるということであり、相続した人はローンの支払い義務が生じます。
一方で、ローンを完済していて抵当権が残っている場合は、相続後に抵当権の抹消登記を行いましょう。またローンが残っていても、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば条件に応じて死亡時に保険金によって完済されるため、ローンを相続する必要がなくなる場合もあります。
抵当権付きの不動産の売却は難しい
抵当権が付いたまま不動産を売却するのは難しいのではと思う方も多いでしょう。抵当権付きの不動産を売却したい場合は、売却時に売買代金でローンを完済し、同時に抵当権の抹消登記を行う方法が一般的なので、そう難しいことではありません。
ただ、抵当権付きでも不動産を売却することは可能なのですが、ローンの残高が不動産の売値を上回る場合は、金融機関の同意が必要となるため債権者との話し合いが不可欠となることを覚えておきましょう。
抵当権を抹消する方法を紹介
抵当権の抹消手続きは以下の流れで行います。
①必要書類を準備する
②管轄の法務局を確認する
③申請書をダウンロードして必要事項を記入する
④法務局に申請して完了
まずは、必要書類を準備します。抵当権の抹消に必要となる書類は以下のとおりです。
・登記申請書
・登記済証または登記識別情報
・登記原因証明情報または抵当権解除証書
・抵当権抹消の委任状
また、登記申請書は法務局にとりに行くこともできますが、ダウンロードして印刷すれば取りに行く手間が省けます。
法務局に申請してから登記が完了するまでは1〜10日かかります。抵当権抹消にかかる費用は登録免許税が不動産1つにつき1,000円なので2,000円~3,000円ほどになります。
不動産担保ローンの金利の種類
不動産担保ローンの金利には固定金利と変動金利の2種類があり、それぞれ特徴や利率の目安が異なります。
ここでは、固定金利と変動金利についてそれぞれ詳しく解説します。
固定金利
固定金利とは、借り入れた時点で決められた金利が返済期間中変わらないことです。毎月の返済額が一定で、返済計画を立てやすい点がメリットです。一方で、変動金利と比べると金利は高く設定される傾向にあります。
将来的な金利変動のリスクを無くし、安定した返済を希望する方におすすめです。
変動金利
変動金利とは、返済期間中に定期的に金利が見直されることです。
一般的に、固定金利よりも金利が低く設定されています。その一方で、状況によっては途中から金利が高くなることもあります。そのため、返済計画を立てにくいことや、返済計画通りに返済できないリスクがあることはデメリットです。
不動産担保ローンの金利の特徴
不動産担保ローンは、無担保ローンと比べると低金利になることや、申し込み先によって金利が変わるなどの特徴があります。不動産担保ローンの金利の特徴を詳しく紹介します。
低金利で借りられる
不動産担保ローンは、他のローンと比べて金利が低く設定されています。これは、住宅や土地などの不動産を担保に差し入れるためです。
適用される金利は、金融機関ごとの商品や申し込み人の与信、担保とする不動産によって変動します。担保にする不動産の価値が高いほど、低金利になる可能性は高くなる傾向です。
申し込み先ごとに金利が変わる
不動産担保ローンは、大別して銀行系とノンバンク系の2種類に分けられます。
銀行系の金利相場は比較的低く設定されていることが多い傾向にあります。ただし、ノンバンク系と比べると審査が厳しく、融資までにかかる時間も長めです。
一方でノンバンク系は銀行系よりもやや高めの金利設定です。その一方で、銀行ほど審査は厳しくなく、スピード融資に対応するケースも多い傾向にあります。
抵当権と金利の関係
不動産担保ローンでは、抵当権の順位によって金利が変わります。具体的には、抵当順位が低いと金利が高くなります。なぜなら、抵当権順位が低いということは金融機関側のリスクが高いからです。抵当順位が低すぎると、不動産担保ローンを断られてしまうケースもあります。
つまり、抵当順位とは一つの不動産に対して複数の抵当権を設定することができるため、登記を行った順番で抵当順位が決まります。したがって、先順位より優先的に弁済を受けることができるため、後順位であればあるほど債権回収の可能性が低くなり、金融機関のリスクが高まります。
不動産担保ローンの金利の決まり方
不動産担保ローンを利用する際、主に以下の要素によって金利が決まります。
・不動産の価値
・返済能力
・融資期間
それぞれについて詳しく解説します。
不動産の価値
担保にする不動産の価値によって金利は変動します。
一般的に、不動産の価値が高いほど金融機関はリスクを軽減できるため、低い金利が適用されます。ただし、不動産の評価方法は金融機関ごとにさまざまです。そのため、申し込む金融機関によって不動産の評価が変わる可能性はあります。
返済能力
返済能力があり、信用情報に問題がない場合は、低金利での融資を受けられる可能性が高い傾向にあります。例えば、「同じ会社に長く勤務してる」「年収が高い」「他に借入中のローンがない」などのケースでは、低金利になる可能性は高いといえます。
また、法人であれば事業で得た収益や会社の経営状況などが判断材料です。業績がよければ、返済能力が高いと判断されます。
融資期間
融資期間を長くすることで金利は高くなる傾向にあります。これは、返済期間が長くなればなるほど金融機関側のリスクが増加するためです。
返済期間を長くすることで金利は上がるものの、月々の返済額を減らすことが可能です。
金利を低く抑えたい場合は、無理のない範囲で返済期間を短くしましょう。
不動産担保ローンならビジネスクルーへ!
ビジネスクルーでは融資事務手数料無料で、最短当日の借り入れができます。返済期間は最長35年と長めに設定できるため、無理のない範囲での返済が可能です。
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀で不動産担保ローンをお探しの方は、ビジネスクルーへお気軽にお問い合わせください。
まとめ
不動産担保ローンを利用する場合、貸付側のリスクを減らすために抵当権が設けられていることがあります。抵当権は金利に影響し、完済後は登記の抹消手続きが必要です。
不動産担保ローンを利用する際は、抵当権について正しい知識を持っておきましょう。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。