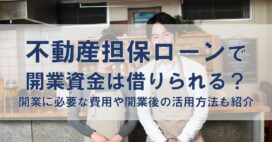インボイス制度とは?概要と確認事項を徹底解説

インボイス制度は、2023年10月から開始されました。インボイス制度の名前を聞いたことがあるものの、具体的にどのような制度なのか、従来の制度と何が違うのか知らないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、インボイス制度の概要と確認事項についてご紹介します。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、2023年10月から開始されました。
インボイスとは「適格請求書」のことであり、インボイス制度が導入されると、売手が買手に一定の要件を満たした適格請求書を発行して双方が保存し、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
適格請求書を発行できるのは適格事業書発行事業者のみであり、適格事業書発行事業者になるためには登録申請が必要です。
参考:国税庁「インボイス制度の概要」
インボイス制度の導入で何が変わった?
インボイス制度が導入されたことで、どのような変化があったのでしょうか。ここからは、インボイス制度の導入で変化した主な事項をご紹介します。
仕入税額控除の適用要件
インボイス制度が導入されることで、仕入税額控除の適用要件が変わりました。具体的に、導入後の要件は売手である取引先から発行された適格請求書を保存している取引のみが、仕入税額控除の対象です。
つまり、適格請求書が発行されない仕入取引は控除の対象外となり、買手側は売上時に受け取った消費税額を全て支払う形となります。
書式
書式の変更もあり、区分請求書から適格請求書に変更されました。適格請求書として認められるためには、一定の要件の項目が記載されていることが条件です。具体的には従来の請求書に適格請求書発行事業者の登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額が追加されている必要があります。
また、先述の通り適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみであり、適格請求書発行事業者以外が発行すると罰則が課せられます。
インボイス制度導入の影響
インボイス制度が導入されると、税額計算方法が一部変わり、経理の事務処理に影響が出ます。では、具体的にはどのような影響が及ぶのでしょうか。
ここからは、インボイス制度導入の影響を詳しく解説します。導入する際、経理業務など影響のある従業員にはしっかりと説明をしておきましょう。
税額計算方法が一部変わる
インボイス制度が導入されると、税額計算方法のうち売上税額と仕入税額の計算方法が変わります。それぞれの新たな計算方法は以下の通りです。
● 売上税額:積上げ計算の特例として、消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額にできます。ただし、売上税額を積上げ計算した場合は仕入税額も積上げ計算にしなければなりません。また、現行の割戻し計算も継続できます。
● 仕入税額:8%の適用税率には108分の100をかけて課税標準額を算出し、さらに税率(6.24%)を掛けて仕入れ税額の算出が可能です。10%の適用税率の場合は、110分の100をかけて課税標準額を算出し、さらに税率(7.8%)をかけます。
経理事務
経理業務が煩雑化されるという影響もあります。仕入先に課税事業者と免税事業者がいる場合、それぞれの事業者に分けて経理処理しなければならないためです。
また、区分記載請求書の記載事項に登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等が追加されます。所定の記載要件を満たしたフォーマットを作成しておく必要があるでしょう。
インボイス制度導入における確認事項
インボイス制度導入を検討している場合、課税事業者と免税事業者それぞれにいくつかの確認事項があります。そこでここからは、それぞれの確認事項をご紹介します。
インボイス制度導入の有無を検討している場合、まずは確認事項をご確認ください。
課税事業者
課税事業者は、以下の項目を確認しましょう。
● 取引先が課税事業者か免税事業者か
● 適格請求書発行事業者の登録
● インボイス発行のフロー
● インボイスの受取と保存のフロー
● 経過措置
インボイス制度導入において必ず確認しなければならないことは、取引先が課税事業者か免税事業者かについてです。適格請求書は課税事業者しか発行できないためです。つまり、取引先が免税事業者ばかりの場合はインボイス制度を導入する必要性は低いといえます。
また、インボイスは適格請求書発行事業者のみが発行できるため、導入する場合は適格請求書発行事業者の登録が必要です。申請は書面のほか電子申請も可能です。登録方法を確認しておきましょう。
さらに、インボイス発行または受け取り及び保存のフローを整える必要があります。フローを整える手順を把握し、スムーズに進められるようにしておきましょう。
なお、インボイス制度には6年間の経過措置が設けられています。課税事業者は、確認事項を確認して経過措置の活用も確認しておく必要があります。
免税事業者
免税事業者は、以下の点を確認しましょう。
● 取引先が課税事業者か免税事業者か
● 課税事業者になるかの検討
免税事業者も課税事業者同様、取引先が課税事業者か免税事業者かを把握しておく必要があります。取引先が課税事業者の場合は仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められる可能性があるためです。ただし、取引先も免税事業者の場合はインボイスを求められることはないため、インボイス制度の導入はさほど必要ないでしょう。
また、取引先に課税事業者が多い場合は課税事業者になるかを検討する必要があります。インボイス制度を導入するメリットと注意点、取引先の課税事業者の割合などを確認し、課税事業者になるかを慎重に検討しましょう。
免税事業者は課税事業者に切り替えるべき?
免税事業者のうち課税事業者に切り替えるべきケースは、取引先に課税事業者が多い場合です。取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除のためにインボイスを求められることがあるためです。インボイスを断ると、取引がなくなったり信頼性が下がったりなどの悪影響を及ぼす可能性があります。取引先の課税事業者の割合や、取引先との関係性などを考慮し、必要に応じて課税事業者に切り替えた方がよいでしょう。
課税事業者に切り替えてインボイス制度を導入すると、取引先と今後も安定的に取引が継続できたり、納税額を売上税額の2割に軽減できる負担軽減措置を3年間受けられたりするメリットがあります。一方で、消費税の納税義務が発生して手取りが減少することや、経理が複雑になる点はデメリットです。
免税事業者を継続した方が良いケース
取引先が個人事業主、またはフリーランスの免税事業者が多い場合は、免税事業者を継続した方が良いでしょう。課税売上高が1000万円以下の個人事業主や免税事業者の場合はインボイスの登録申請をする必要がないので、インボイスの発行を求められる可能性もないためです。
免税事業者を継続することで、従来通り消費税の納税義務が発生することはなく、売上が変わらなければ消費税の納税もないため、その分手取りが減らないというメリットがあります。一方で、仕入れ額控除の対象にならないため、取引先から値引きを交渉される可能性や、課税事業者の競合他社に負ける可能性もあります。
インボイス制度導入に活用できる補助金制度
インボイス制度を導入する場合、補助金制度を有効に活用することで金銭的負担を軽減できます。そこで最後に、インボイス制度導入に活用できる補助金制度を2つご紹介します。
IT導入補助金
中小企業や小規模事業者の業務の効率化、売上アップのサポートを目的に、ITツールを導入する費用負担を減らすために作られた補助金制度です。
インボイス制度導入においては、インボイス導入を見据えた会計ソフトや受発注ソフトなどの導入が対象であり、「デジタル化基盤導入枠」が設けられています。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金にも、インボイス枠が設けられました。小規模事業者持続化補助金のインボイス枠では、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける際にかかる費用を補助してもらえます。
まとめ
インボイス制度の導入は、取引先との関係性にも影響するため非常に重要です。インボイス制度の概要や、導入後の影響などを理解した上で、インボイス制度を導入するか否かを慎重に判断しましょう。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。