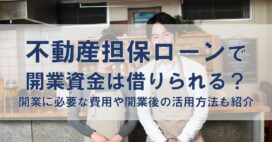中小企業にとってのインボイス制度とは?準備しておくことは?

取引時に適格請求書を利用することで、仕入税額の控除が受けられるインボイス制度。インボイス制度の導入で消費税の取り扱いに関して複数の変更点があり、中小企業でも影響を及ぼす可能性があります。
そこで今回は、中小企業にとってのインボイス制度と、準備しておくことをご紹介します。
目次
インボイス制度開始に伴う中小企業への影響
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額の金額を正しく計算するための制度です。インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行して取引をすることで仕入税額の控除が受けられるのです。
インボイス制度の導入で、請求書や納品書などの記載項目が変わります。また、消費税の端数処理がルール化されるなどの変更点があります。これらの変更で、事務処理の煩雑化が予想されるでしょう。
課税事業者のみが適格請求書発行事業者として登録申請できる
インボイス制度を利用するためには、適格請求書が必要です。ただし、適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、課税事業者のうち適格請求書発行事業として登録された事業者が対象です。つまり、非課税事業者が売り手の取引ではインボイス制度が適用できず、仕入税額控除は受けられません。
非課税事業者がインボイス制度を適用する場合は、課税事業者になる必要があります。
すでに課税事業者で、インボイス制度を利用したい場合は、適格請求書発行事業者の登録申請をしましょう。
中小企業が適格請求書発行事業者になるために必要な準備
中小企業が適格請求書発行事業者になるためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。この際、非課税事業者は適格請求書発行事業者の対象外となるため気をつけましょう。
登録されると税務署からインボイスの登録番号等が記載された登録通知が送付されます。登録番号は法人の場合は「T+法人番号」、個人事業主は「T+13桁の数字」です。登録番号は適格請求書を発行する際に記載します。
また、取引先の確認も大切です。適格請求書発行事業者であるかを確認し、適格請求書発行事業者でない場合は経過措置を含めて取引の継続を検討しましょう。
中小企業が適格請求書発行事業者にならなかった場合の影響
インボイス制度が開始されたからといって、適格請求書発行事業者になることは義務ではありません。なぜなら、取引先が非課税事業者ばかりの場合は不要です。
前述の通り、非課税事業者はインボイス制度を利用できません。そのため、自社が適格請求書発行事業者だとしても、相手が適格請求書発行事業者でなければインボイス制度の対象外です。
一方で、適格請求書発行事業者でないことで取引先との関係が切れたり、競合他社に取引先を取られたりする可能性があります。取引先が課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者にならないことの影響を考慮しましょう。
中小企業が適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット
中小企業が適格請求書発行事業者になることで、取引先の求めに応じて、適格請求書を発行できます。取引先の選定において、適格請求書発行事業者であることが条件のひとつになると考えられます。そのため、既存の取引先との継続に影響を及ぼさない点はメリットです。また、適格請求書発行事業者であることが新規取引先の獲得につながる可能性もあります。
一方で、適格請求書発行事業者になるデメリットは、追加で発生する経理作業といえるでしょう。なぜなら、仕入税額控除を受ける要件が変わり、受け取った請求書は適格請求書と非適格請求書の仕分けが求められるためです。そして、適格請求書を発行する際には、記載項目が追加されたことによる作業が増加します。
加えて、これを機に非課税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、消費税の納税義務が生じ、納税事務の負担が増加します。
中小企業が適格請求書発行事業者になるとさまざまな影響がある
インボイス制度において、適格請求書発行事業者になるかの判断はあくまで事業者の任意です。とはいえ中小企業や小規模事業者にとっては、経営に直結する問題となるため慎重な判断が求められます。
インボイス制度の影響はさまざまな場面に及ぶため、インボイス制度について正しい知識や理解を深め、メリット・デメリットを比較し、よく検討しましょう。
まとめ
適格請求書を発行することで、仕入税額の控除が受けられるインボイス制度。インボイス制度の導入には、メリットとデメリットがあります。
自社が課税事業者か非課税事業者かはもちろん、取引先との関係も考慮して適格請求書発行事業者になるか否かを判断しましょう。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。