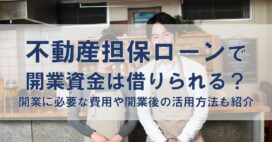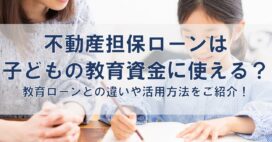節税にも有効な不動産の減価償却!その仕組みや計算方法について
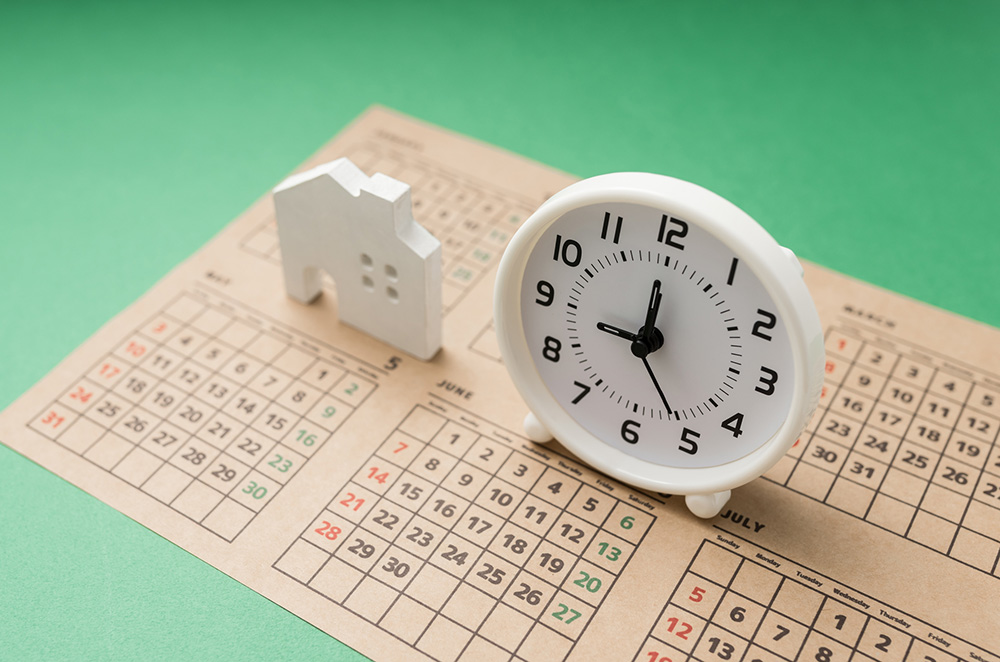
投資を目的とした不動産の購入を考えているのであれば、必ず知っておきたいのが「減価償却」です。
減価償却は節税対策にもつながる重要な会計手続きとなりますが、詳しい内容や計算方法まで正しく理解できていない人も多いことでしょう。
この記事では、不動産の減価償却の仕組みや計算方法などについて詳しくご紹介いたします。
目次
どのような仕組み?対象となるのは?不動産における減価償却の基礎知識
減価償却とは、固定資産における会計処理手続きのひとつです。
将来的に資産価値が下がることを考慮し、損失となる分を毎年、減価償却費として経費計上できるようになっています。
これは不動産も対象となっていて、上手く活用すれば節税につなげることも可能です。
ただし、不動産といっても対象となるのはあくまで建物のみで、土地は基本的に経年劣化による価値の低下がないため、対象には含まれません。
このほか、減価償却費の計上方法は、法定耐用年数によって違ってきます。
法定耐用年数とは、建物の構造や用途、経過年数によって法令で定められている年数です。
実際に建物が持ちこたえられる期間を意味する「耐用年数」とは異なるため、注意しておきましょう。
減価償却費の計算方法
固定資産の減価償却費を計算する方法には定額法と定率法の2種類があり、どちらで計算するかは資産区分に応じて決められています。
この2種類はその名の通り計算方法が異なるため、それぞれの特徴などを詳しく知り、まずは減価償却費を正しく計算できるようになることが大切です。
毎年の減価償却費が均等となる定額法
定額法とは、原則として毎年同じ金額で減価償却費を計上していく計算方法です。
主に建物やそれに付属する設備、ソフトウェアなどの減価償却費を算出する際に使用されます。
ここで忘れてはいけないのが、以前までは建物を対象とする不動産の減価償却についても定率法を選択することができましたが、税制改正によって、平成10年4月1日以降に取得した建物に対する計算式は必ず定額法を用いるということです。
この定額法では、取得原価を法定耐用年数で割ることにより減価償却費を算出します。
しかし、実際に計算すると必ずしも割り切れるとは限らず、割り切れなかった場合には償却率を使って計算します。
計算式は「取得価格×償却率」です。
償却率は「1÷償却年数」で算出し、割り切れなかったときには小数点以下第4位を繰り上げます。
たとえば、事務所として使用する木造の建物の場合、耐用年数は24年なので、計算式は「1÷24」となりますが、この式で計算すると「0.04166667」の後も数字が続き、割り切れません。
そのため、小数点以下第4位で繰り上げて償却率は「0.042」とします。
ただし、ルール通りに計算しても減価償却できる最後の年度の期末価格は0円になりません。
固定資産があったことを示すために、最後の年度は端数を調整し、1円だけ残すのが決まりとなっているからです。
最終年度の減価償却費はほかの年度と同じ金額にならないため、その点に注意しましょう。
減価償却する割合が一定となる定率法
先に記述したように、現在は建物の減価償却費の計算に定率法は選択できませんので、あくまで予備知識となりますが、定率法は減価償却する割合が一定となった計算方法です。
主に自動車などの減価償却費を算出する際に使用されます。
毎年の金額が同じとなる定額法に対し、定率法は未償却の残高に償却率を掛けることで、その年度の減価償却費が算出されます。
定率法で計算する際に使用する償却率は定額法の償却率の2倍ですが、最終年度の額は1円残すことがルールとなっています。
しかし、この償却率に基づき減価償却していくと、最終年度を1円にすることができません。
そこで、償却年数ごとに定められている保証率や割合の高い改定償却率を用いて調整し、取得価格に保証率を掛けた額よりも、定率法で算出した減価償却費の額の方がが低くなる時は改定償却率を用いて計算し、1円まで強制的に減価償却するという仕組みです。
節税効果を高めたい!減価償却費をより多くするための方法
減価償却費は経費に含めることができるため、多く計上できれば節税につなげることが可能です。
たとえば、取得金額が同じ物件でも、土地より建物の価格割合が大きいものの方が減価償却費を多く計上できることになります。
重要なのは減価償却の対象となるのがあくまで建物だけということです。
また、減価償却費の計算式では、耐用年数が短いものの方が減価償却費は大きくなります。
ただし、耐用年数が短いということはそれだけ資産の価値が減少するのが早いということです。
時間の経過に伴ってその分、売却時に価格が下がる可能性もありますので、注意しておきましょう。
投資物件は節税対策も大切!減価償却を上手く活用しよう
投資目的で不動産を購入する際には、投資物件から得られる利益だけに目を向けるのではなく、減価償却費も含めて総合的にどれだけの利益を得られるかまで、きちんと計算しておくことが大切です。
償却期間内であれば支出もなく、毎年経費計上できる減価償却について、仕組みや計算方法をしっかりと理解し、上手に活用して節税対策を行いましょう。
この記事の監修者
- 株式会社ビジネスクルー
- 代表取締役 浅山 亮二
- 2007年10月に株式会社ビジネスクルーを設立。
近畿一円を中心に、個人向け・事業者向け・不動産業者向けに不動産を担保とする融資サービスを提供。
貸金業務取扱主任者及び宅地建物取引士の資格を保有。